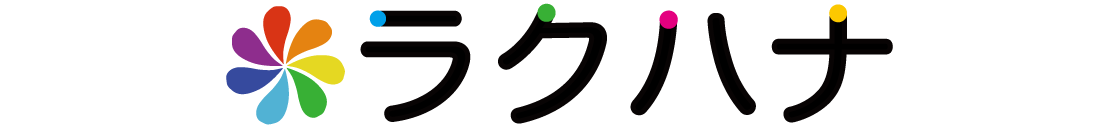お盆は、日本独特の風習です。
仏教と神道が融合した、先祖の霊を祀る日本の行事です。
江戸時代までは、お盆は旧盆に行われていました。
日本では江戸時代まで、月の満ち欠けをもとに割り出した旧暦(太陰暦)を用いていました。
お盆は、旧暦の7月15日に行われていました。
明治時代に入り、明治政府は明治6年に、世界標準のグレゴリオ暦を新暦として採用しました。
お盆も自動的に新暦になったのですが、新暦の7月15日は農繁期で地方は忙しい最中。
それで東京を中心とした都市部のお盆は新暦の7月15日になりましたが、地方は1か月遅れのお盆として、新暦の8月15日のお盆となりました。
地域によっては、養蚕の農閑期の8月1日にお盆をしたり、昔の旧暦でしているところもあります。