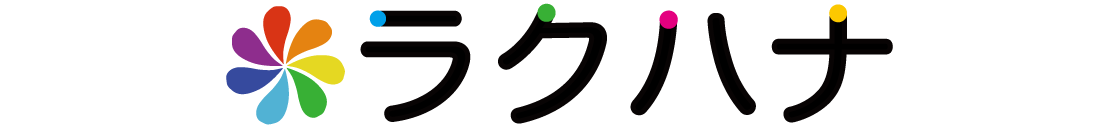春と秋の年2回、お墓参りをしてご先祖様を敬う「お彼岸」。
この期間、仏壇を清め、おはぎやぼたもちを供えるという習慣は、日本特有のものと思われがちです。
しかし、「亡くなった人を偲び、感謝を捧げる」という心は世界共通。形や時期は違えど、日本のお彼岸や盆と共通するような、先祖供養の特別な期間を持つ国や文化は数多く存在します。
ここでは、日本のお彼岸(またはお盆)と特に似た風習を持つ海外の行事をご紹介します。
アジア圏:ルーツを共有する「先祖崇拝」の文化
東アジアの国々では、儒教や仏教の影響を強く受けており、日本と共通の祖霊信仰が見られます。
1. 韓国:「秋夕(チュソク)」
- 時期: 旧暦の8月15日(中秋節)。日本の**「お盆」**とほぼ同じ時期にあたります。
- 内容: 収穫を祝うとともに、先祖に感謝を捧げる大切な祝日です。家族全員が故郷へ帰り、先祖の墓を訪れて掃除をし、**祭祀(チェサ)**と呼ばれる供養の儀式を行います。この時期に交通渋滞が発生する光景は、日本の帰省ラッシュとよく似ています。
2. 中国:「清明節(チンミンジエ)」
- 時期: 毎年4月4日または5日ごろ。日本の**「春のお彼岸」**と近い時期です。
- 内容: 故人の墓を清め、供養する伝統的な行事で、**「掃墓節(そうぼせつ)」**とも呼ばれます。家族でお墓参りに行き、線香や紙のお金(冥銭)などを供えます。日本の彼岸のように、先祖を敬い、自然の恵みに感謝するという意味合いを持ちます。
3. 中国・台湾:「中元節(ちゅうげんせつ)」
- 時期: 旧暦の7月15日ごろ。日本の「お盆」と結びつきが深いです。
- 内容: 仏教の盂蘭盆と道教の信仰が結びついた行事です。霊界の扉が開き、この世に戻ってくる霊をもてなすと考えられており、紙銭を燃やしたり、食べ物を供えたりといった儀式が行われます。
欧米・中南米:死者と再会を祝う「賑やかな祭り」
アジア圏とは異なり、カトリックの影響が強い国々では、死者を悼むだけでなく、共に再会を祝うような明るい祭りとして定着している風習があります。
メキシコ:「死者の日(Día de los Muertos)」
- 時期: 毎年11月1日と2日。
- 内容: 日本の**「お盆」と最も共通点があるとされる行事です。故人の魂がこの世に戻ってくると信じられています。しかし、日本の静かな雰囲気とは対照的に、メキシコではカラフルな骸骨のモチーフで街中が飾られ、賑やかなパレードやパーティーが行われます。各家庭では、故人の好物や「死者を導く花」とされるマリーゴールド**を飾った祭壇(オフレンダ)を作り、故人を盛大に迎えます。
ヨーロッパ:「諸聖人の日(All Saints' Day)」など
- 時期: 11月1日と2日(キリスト教の行事)。
- 内容: カトリック圏の多くの国で、亡くなった人々を追悼する日とされています。この時期に家族が墓地を訪れ、花やキャンドルを供えて祈りを捧げる習慣は、日本のお墓参りと通じるものがあります。元々ケルト人の風習であった**ハロウィン(10月31日)**も、古代は死者の魂が戻る日とされており、先祖供養のルーツを持っています。
「供養の心」は世界共通
国や宗教、文化によって、墓を清める(清明節)、賑やかに迎える(死者の日)、収穫と感謝を捧げる(秋夕)など、行事の形はさまざまです。
しかし、「亡くなった家族や先祖を敬い、感謝を伝え、今を生きる自分たちを見守ってくれる存在として大切にする」という根底にある「祖霊信仰」の心は、アジア近隣の中国・台湾・韓国のみならず、海を越えて共通していると言えるでしょう。
日本のお彼岸が、太陽と先祖への感謝を捧げる静謐な期間であるように、世界の各地でも、人々はそれぞれの方法で、大切な故人との絆を感じる特別な時間を過ごしています。